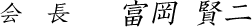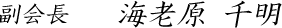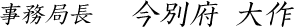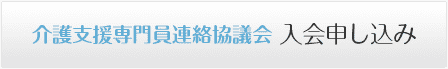協議会概要
会長挨拶
会員の皆様方におかれましては、日頃より当協議会の活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルスに振り回され続けた3年間でしたが、この5月から感染症法上の分類が5類に変更となり、新たなステージに移行することになりました。私たち介護支援専門員も動きに制約がある中で、非常に厳しい時期を過ごしてきましたが、今後は、感染症とも上手に付き合いながら、業務に当たっていかなければなりません。
当協議会でも、会員同士のつながりが希薄化していると感じています。コロナ禍の中でリモート研修も定着してきましたが、今後は参集型の研修も徐々に再開し、会員同士の連携強化が図れることを期待しています。
一人のケアマネジャーだけではできないこと、一つの事業所だけではできないことも、500名を超えるこの組織ではできることも沢山あるのではないかと思います。会員の皆さん全員の力を結集し、この協議会がますます発展していくこと切望いたしますし、そのために私たち役員も尽力していきたいと思います。皆さん、今後ともご協力の程、よろしくお願いいたします。
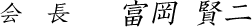
副会長挨拶
新型コロナ感染症の流行において、私達の生活や介護支援専門員としての業務や支援も変化してきたと思いますが、基本は利用者様に寄り添い、自立支援を目標にその人らしく生活が豊かになるよう今後も心掛けていきたいと感じております。
介護支援専門員に課せられる知識や資質向上、益々重要な役割を担っています。行政や医療、多職種との連携、又、地域にも目を向けていかねばなりません。感染や災害に対する業務継続計画(BCP)も今年度中に作成しなければなりません。
日々業務に追われている会員の皆様と研修会等を通し、スキルアップ出来るよう取り組んでまいります。今後もご協力のほど、よろしくお願い致します。
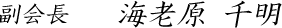
事務局長挨拶
平素より皆様方におかれましては、当協議会の運営に多大なるご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。これからの2年間、事務局長を仰せつかりました今別府と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、介護保険制度は2000年にスタートし23年目となりました。宮崎市の第8期介護保険事業計画である「宮崎市民長寿支援プラン」は最終年度を迎え、各地域において地域包括ケアシステムの推進が図られていることと思いますが、令和2年1月に国内で感染が確認された新型コロナウイルス感染症の影響により、私たちの生活はこれまでと一変し、地域包括ケアシステム構築においても大きな影響を与えたのではないでしょうか。しかしながら、この新型コロナウイルス感染症によって、地域包括ケアシステムの推進状況が見えた部分もあるのではないでしょうか。介護保険制度の要である介護支援専門員がそれらの課題から今後取り組むべきことを提案し、有事の際にも機能する地域包括ケアシステムの推進に取り組んで参りましょう。
また、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上の分類で2類相当から5類へと引き下げられ、次年度は介護保険制度などトリプル改定がございます。変化の多い近年ではありますが、その流れに乗り遅れないよう、会員の皆様にタイムリーな情報提供と介護支援専門員としての質の向上、また会員同士の横のつながりが作れるよう協議会活動を展開してまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
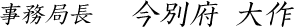
役員名簿
| 役職 |
氏名 |
勤務先 |
| 会長 |
富岡 賢二 |
特別養護老人ホーム悠楽園 |
| 副会長 |
海老原 千明 |
ケアライフかなえ |
| 事務局長 |
今別府 大作 |
小規模多機能型居宅介護 芳生あやめ館 |
| 会計 |
岩切 尚美 |
居宅介護支援事業所ほたる |
| 会計 |
冨山ハルミ |
宮崎市住吉地区包括支援センター |
| 理事(広報・渉外) |
村山 圭太 |
一般財団法人弘潤会 野崎病院 |
| 理事(施設支援研修) |
長友 崇稔 |
グループホームさんあい |
| 理事(相談・サポート) |
投山 誠志郎 |
宮崎江南病院付属居宅介護支援センター |
| 理事(スキルアップ研修) |
中島 晋太郎 |
特別養護老人ホーム城ヶ崎小戸の家 |
| 監事 |
坂本 増美 |
社会福祉法人新和会 |
| 監事 |
牛谷 義秀 |
クリニックうしたに |
| 監事 |
楠元 剛志 |
元)たかおか居宅介護支援事業所 |
| 顧問 |
嶋田 喜代子 |
元)宮崎市木花・青島地区地域包括支援センター |
| 事務局 担当 |
山内秀一郎 |
宮崎在宅介護支援センター |
入会のしおり
入会のしおり・・・PDF(約550kb)